
生物多様性の危機第1の危機(開発など人間活動)

開発による影響
長野県版レッドリスト(2014年)では、植物の絶滅危惧要因として、開発行為や森林伐採が28%にのぼっています。
また、魚類、水生昆虫類、貝類など水辺環境に生息する生き物は、陸上に暮らす生き物に比べて環境変化に対して逃げ場が少ないため、開発などによって大きな影響を受けやすいといえます。
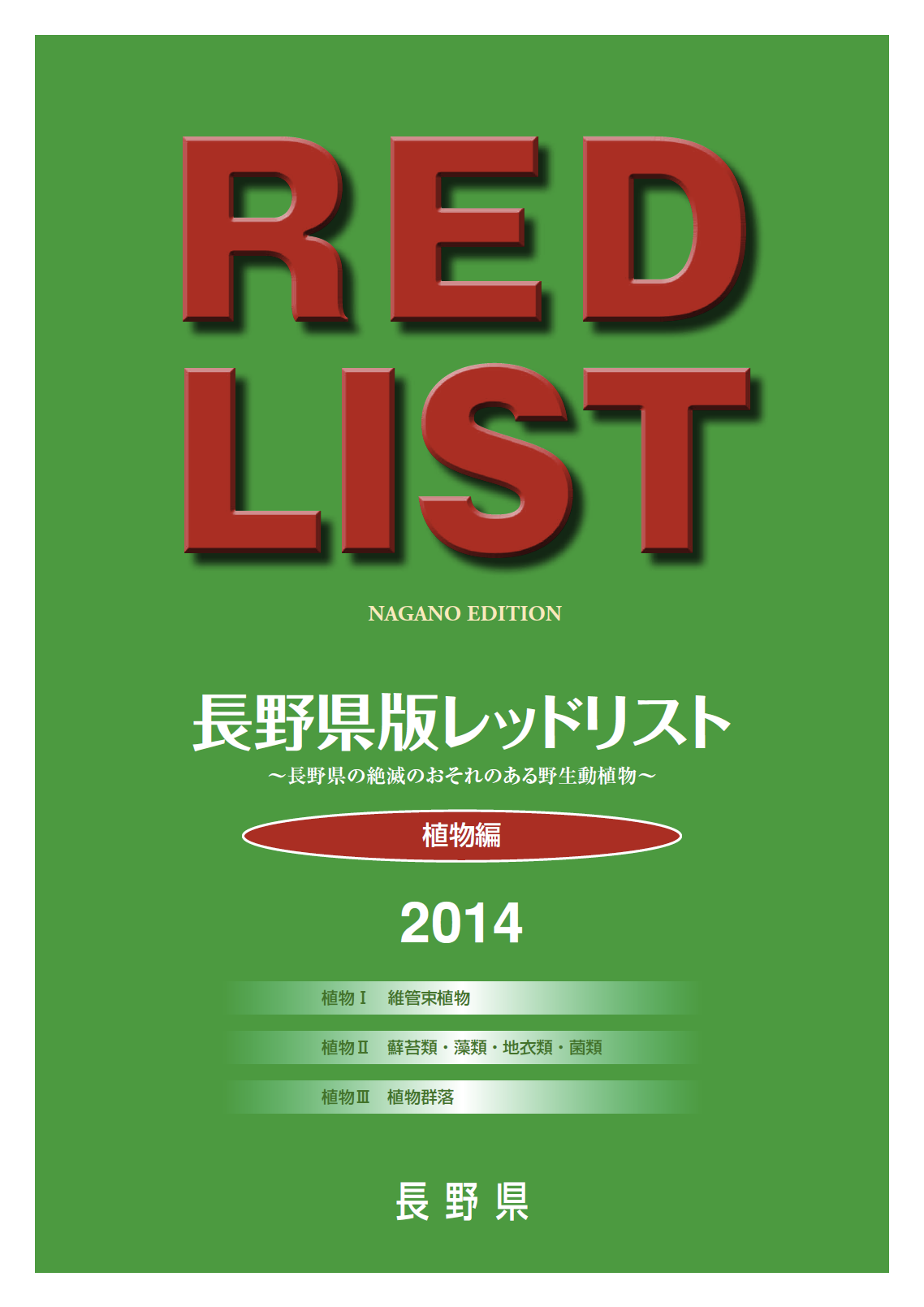
乱獲・盗掘・違法捕獲による影響
野生生物を捕獲・採取によりとりすぎてしまうと、その生き物の数や生息・生育場所に悪影響をもたらすことがあります。長野県で絶滅したニホンオオカミやニホンカワウソ、トキは、絶滅した要因のひとつとしてかつての過剰な狩猟や駆除の影響が大きかったと指摘されています。
最近では、ラン科やサクラソウなどの植物に対する園芸や観賞を目的とした採取(違法捕獲を含む)による影響が大きくなっています。
違法採取・捕獲の被害が多い種



動物では、オオルリシジミやオオイチモンジなど、希少な昆虫の違法捕獲が発生しています。

踏みつけによる影響
山岳県である長野県では、登山道沿いの植物等の「踏みつけ」が大きな問題となっています。
「踏みつけ」とは、人間によって地表面に生える植物が踏まれることによりダメージを受ける被害を指し、多くの登山客が訪れるところで顕著となります。
特に高山帯や湿原に生育する植物は踏みつけによるダメージが大きく、一度大きなダメージを受けてしまうと、その回復には長い期間がかかります。

【外部リンク】
長野県の希少野生動植物について
